 �@�@
�@�@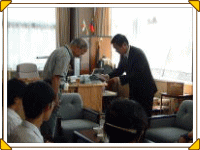 �@
�@�T���A�h���v���O�����T�v
�W���P�P���i���j�@�݊y�����ɏo���̈��A
 �@�@
�@�@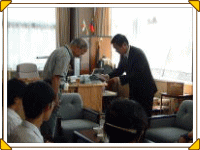 �@
�@
�@�T���A�h���o���̈��A�̂��߁A�c�����Z�Z���ƂƂ��ɐ݊y�������K�₵�A�݊y�����Ƃ�������B��������Z���֔h���˗�������n���Ă�����������A�R�O�����x���k�������B���k����͈�l��l�A����̔h���ɑ�����������`�������B�����́A���[���A�������Ȃ���g�������サ�ĉ��������B
�W���P�S���i���j�@�o�������E�O���ȖK��
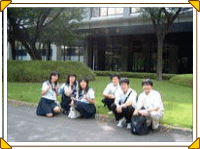 �@�@�@
�@�@�@
�E������
�@�ߑO�P�O���O�ɖ{���w�ɏW�����A�L���ցB�V�����ɏ�芷���A�����Ɍ������B�Ԓ��ɂāA�e�K���ł̑�\���A�ƋL�^��������̕��S�����߂��B�����w�ł́A���ۃt�����h�V�b�v����i�ȉ��AIFA)�̕����z�[���ɏo�}���āA�O���Ȃ܂ňē����Ă����������B
�E�O���Ȃ�
�@�O���Ȃɓ����B�O���ȃ��r�[�ɂ�IFA��ƍ��������B���炭���ĐE���̕��Ɉē�����āA�O���ȒS�����̕��X�ƑΖʂ��A�u���[�t�B���O���s�����B����̃v���O�����̖ړI����������Ɗm�F���A�����ƈقȂ鉿�l�ς��~�߂ď�Ɋw�Ԏp����Y��Ȃ��悤�ɁA�Ƃ̂��b�����B
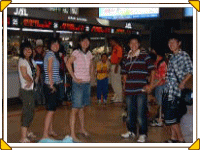
�E���c��`��
�@�O���Ȃ��o�����A���c��`�ցB��������͊O���Ȃ̕������s���Ă����������B
�@��`�ɓ�������ƁA�O�����Ĕz�����Ă������X�[�c�P�[�X�����A���ւ����ς܂��`�F�b�N�C���B�o���R�����o�ďo�����r�[�ֈړ��B��s�@�͌ߌ�V���ɗ\��ʂ藣�����A��H�t�B�W�[�ւƌ������B
�W���P�T���i�j�@�t�B�W�[�@�`�@�T���A����
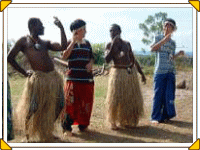 �@�@�@
�@�@�@
�E�t�B�W�[���w
�@��H���X���Ԏォ�����āA�t�B�W�[�̒��V������i���f�B��`�ɓ����B���{�Ƃ̎����́{�R���ԁB���{�l�K�C�h�̕����o�}���Ă�������A�ԂQ��ɕ��悵�Ďs���֏o���B�L��ȃT�g�E�L�r�������ڂɁA�`�p�{�݁A�T�g�E�L�r�����H��Ȃǂ�����A�t�B�W�[��Q�̊X���E�g�J�ɓ����B�����A�n���̃}�[�P�b�g�ɓ���ƁA���������ʕ������X�Ɩڂɓ����Ă����B�t�B�W�[�̐l���̔����߂��̓C���h�l�������ŁA�}�[�P�b�g�Ŏ��H�����X�B�[�c���C���h�̂��َq�ł������B
�@���ɁA�����ȑ���K�ꂽ�B�����Ńt�B�W�[�`���̃��{���������w�A���H�����B���{�����Ƃ́A�Ă����̏�ɐH�ނ��ڂ��A����Ƀo�i�i�̗t�Ȃǂ���ɍڂ��ď����Ă��ɂ��闿���ł���B���H�̌�A�u�J�o�i�q�����ĂȂ��ۂ̓`���I�Ȉ��ݕ��j�̋V���v��̌����A���̐l�X�Ɗy�����̂��A�x�����B�܂��A���q�̔���g�����w�A�o���h�����̌������B
�@�i���f�B�ɖ߂�r���ŁA���{��ODA�Ō��݂��ꂽ�t�B�W�[�C�ۑ�ɗ���������B�����ł́A���{����V�j�A�{�����e�B�A�ŗ��Ă�������ٓ����ē����Ă����������B
�@�i���f�B�ɖ߂�A�[�H�̌�A��`�ցB�ߌ�P�O���Q�T���A���悢��T���A�Ɍ������B

�E�Ƃ��Ƃ��T���A�ɂ���ė���
�@�i���f�B��`����P���ԂS�O���̃t���C�g�ŁA�T���A�E�A�s�A��`�ɓ��������̂́A���v���߂��ē����̌ߑO�P���T���B���t�ύX���������߂ł���B���{�Ƃ̎����́A�|�Q�O���ԁB��`�ɂ́A�z�e���E�L�^�m�Ɨ��s��Ѓp�V�t�B�b�N�E�C���^�[�i�V���i���̕��A����ɂ͌��n��ƃ��U�L�E�T���A�ɂ��߂̓c�����ZOB�̕����o�}���Ă����������B�z�e���Ɉړ����A�ו������Ă悤�₭�A�Q�B

�E�O��f�Տȕ\�h�K��
�@�����P�Q���Ƀz�e���̃��r�[�W���B���H��A�O��f�ՏȂ�\�h�K�₵�A����b�Ɖ�����B���ɒg�������}���Ă�������A��X����̎���ɂ����J�ɉ����Ă����������B
 �@ �@
�@ �@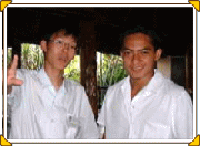 �@�@
�@�@ 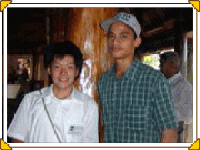 �@�@
�@�@
�E�z�X�g�t�@�~���[�Ƃ̏��Ζ�
�@�����b�Ƃ̉�͂P�W���ɉ����ƂȂ������߁A�S���҂ɂ��y�Y�����n�����đ��X�ɑގ����A�z�e���ɖ߂����B
�@���̌�A�z�X�g�t�@�~���[�Ƃ̏��߂Ă̑Ζʂ�����B������r�[�ɂ܂�ŋ��m�̒��ł���悤�ȗl�q�B�T���A�̍��Z���̕��͋C���ƂĂ��ǂ��������炾�낤�B���Ƃ��ƁA�l��g��������镶���I�y�낪����̂�������Ȃ��B���{�l���ǂ����ɖY��Ă����S�ɁA�����T���A�̒n�ŏo������C�������B�@
�W���P�U���i���j�@�A�x���J���b�W�K��
 �@�@�@�@
�@�@�@�@
�E�A�x����J���b�W�Œ��̏W��ɏo��
�@�A�x����J���b�W�ł͒����̂Ō}����B���ɗǂ������n��B�������̐��ɋ����A�܂��A���k�̃��[�_�[���w��������A�S�̂��悭�܂Ƃ߂Ă������Ƃɂ����S�����B
�@�ւ���āA������̔ԂƂȂ�B���O�ɏ��������ʐ^�����g���A���{�̂��ƁA�݊y���̂��ƁA�c�����Z�̂��Ƃ��Љ���B�Ō�ɏ����̎������s�����B�T���A�̐��k�B�̖��O���āA������Ђ炪�Ȃŏ����Ă������肵���B����������ꂽ�悤�ŁA���̌�̎��ƎQ�ςł��A�����Ԃ�����̃T���A�̐��k�B����A���O����{��ŏ����Ă���Ɨ��܂ꂽ�悤�ł���B
�E�V�l�z�[���ƃX�e�B�[�u���\�������ٌ��w
�@���Ɍ��������̂́A�߂��ɂ���V�l�z�[���B�ꏏ�ɍs�����T���A�̐��k�ɂ��ƁA��������ɂ������p�͖������������B�����̂ƂȂ��Ă���悤�ŁA�C�̌�����u�ɂ��葐�Ԃɖ������������ꏊ�ł������B
�@�����ăX�e�B�[�u���\�������ق����w�B�u�v�̒��҂Ƃ��ėL���ȃX�e�B�[�u���\���́A�T���A�ł��̐��U������B���̔ނ����O�ɉƑ��ƕ�炵���@��A�����قƂ��Ĉ�ʂɌ��J����Ă���B�C�������낷�R�̒��ɂ���m�ق͂ƂĂ��L���A���邢���͋C�ł������B
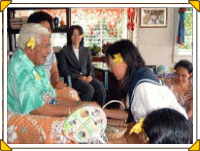
�E�T���A���ƌ���@��\�h�K��
�@�Ȃ�ƃT���A���ƌ���ł���A�}���G�g�A�E�^�k�}�t�B�� II���ɂ���ł����B�A�x����J���b�W�̍Z���搶�̂����l�Ƃ͂��w�F�ł���Ƃ̂��ƁB�T���A�̐l�ł��Ȃ��Ȃ��������@��Ȃ������ŁA�ォ��T���A�̎����ɂ��̂��炪�������Ă���̂����āA�{���ɋ������B�T���A�Ɠ��{�̍��Z���̖K���S������ʼn�����A�I�n�Ί�Őڂ��Ă����������B���ژb���ł��邱�Ƃ��H�����������A�������Ă����A�����Ă����������B
�������P�X�N�T���P�Q���i�T���A���ԂP�P���j�ɁA�}���G�g�A�E�^�k�}�t�B���U�����ƌ��A��s�A�s�A�ɂĂ���������܂����B���N�X�T�B�y�������Ă������������̏Ί炪����̂悤�Ɏv���o����܂��B�����ɁA�ނ�ł�����ݐ\���グ�܂��B
�W���P�V���i�j�@���{����̉����̎��ۂ����w
 �@�@�@�@
�@�@�@�@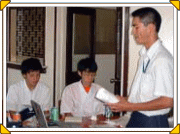
�EJICA�K��
�@���̓��́AJICA���͂��߁A�N�C�O���͑���V�j�A�{�����e�B�A�Ƃ��Ď��ۂɃT���A�Ŋ������Ă�����X��K�ˁA���{����̓I�ɂǂ̂悤�Ȏx�����s���Ă���̂����w�B
�@�܂���JICA��������K��B���{�́A�T���A�ɑ��鉇���̊T�v�ɂ��Đ��������B���O�Ɋw�K�͂��Ă������A��͂茻��œ������X����̏��͂���̓I�ł������B�����Ő��k�́A���{����̎x����g�߂Ɋ����邱�Ƃ��ł����悤���B
�@����JICA�̕��X�Ƌ��ɁA�T���A���ȂōL���Ɍg���i�n�b�u�̐ԍ肳���K��B�T���A�̊��������ɁA���܂��܂Ȗ₢���������Ă��Ă�������A���߂Ċ��ɂ��čl����悢�@��ƂȂ����B
�@�����ĖK�ꂽ�E�ƌP���Z�h���E�{�X�R�ł́A�V�j�A�{�����e�B�A�Ƃ��Ď����Ԑ����������Ă�����ɂ�������B�����ł́A���i�O���̐l�X�ɗ]���I���Ȃ����k�Q�U�O�]���ɂ��唗�͂̃T���A�_���X�������Ă����������B


�E���U�L�E�T���A�H�ꌩ�w
�@���ɁA���{�̎����ԕ��i�����H��u���U�L�E�T���A�v��K�₵���B���U�L�͐݊y���ɂ��H�ꂪ����A�c�����Z�̂n�a�̕����݂����Ђł���B
�H��ɒ����ƁA�]�ƈ��̊F���̂ƃ_���X�Ŋ��}���ĉ��������B���Ƃ̊T�v�ɂ��Đ����������ƁA�T���A�������ɏo�}���ĉ��������c�����Z�n�a�̕����H������ē����Ă����������B���Ȃ��K�͂ȍH��ŁA���̊�Ƃ��T���A�o�ς��x���Ă�����̂̂P���A�Ƃ����b�ɔ[�������B
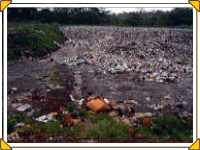 �@�@�@
�@�@�@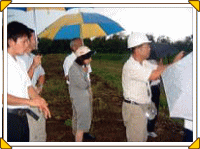
�E���������ݖ��������ꌩ�w
�@�Ō�ɖK�ꂽ�̂��A���O�w�K�ł��w���������ݖ���������B�T���A�ɂ�����S�~�����̒��S�{�݂ł���B�����ł����{����V�j�A�{�����e�B�A�ŗ��Ă�����������A���̕��̈ē��ŃS�~�����{�݂����w�����B���̎{�݂̐ӔC�҂͓��{�ŋZ�p���C�����T���A�̕��ł������B���݁A�ނ𒆐S�ɃT���A�̂��ݏ�����肪���悢�����ւƐi��ł��邱�Ƃ�m��A�l�ނ��琬���鉇���������ɏd�v�ł��邩���m�F�ł����B
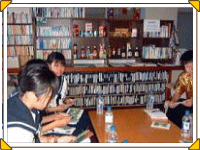
�E�p�V�t�B�b�N�E�C���^�[�i�V���i��
�@����̊e�K���ւ̘A��������͂��߁A�T���A�����ł̈ړ��ł����b�ɂȂ����A���s��Ѓp�V�t�B�b�N�E�C���^�[�i�V���i����K�₵���B�T���A�̒j���ƌ�������Q�O�N�ԃT���A�ɂ�����������Ƃ�����A�T���A�ɗ��������̃A�s�A�̗l�q��T���A�ł̕�炵�ɂ��Ă��b�����Ƃ��ł����B
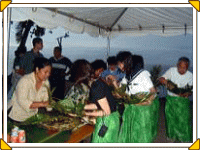
�E�C�ӂŃE��������H��
�@�A�x����J���b�W�̍Z���搶���A�������C�ӂɃT���A�`���̏��������E����p�ӂ��Ă����������B�Z���搶�̎w���ŁA�X�e�C��̍��Z�������S�ɏ��������Ă��ꂽ�悤���B����Ȕ������ꏊ�łƂĂ����������H�������������A���ɍK���ȂЂƂƂ����߂������Ƃ��ł����B
�@�������A�����Ŗ�肪��B�X�e�C��ʼn߂����Ō�̖�Ƃ������Ƃ�����A�X�e�C��ɋA��Ƃǂ̉ƒ�ɂ�����ɂ��������[�H���҂��Ă����̂��B�܂�A��قǂ̃E�������͂���B�F�̑̏d���������̂́A�܂��ԈႢ�Ȃ������ł���B
�W���P�W���i���j�@�ʂ�̓�
 �@�@�@
�@�@�@
�E����E�X�|�[�c�E�����Ȃ�K��
�@���悢��T���A�ŏI���B���X���Ƀz�e���E�L�^�m�ɏW���B�z�X�g�t�@�~���[���F�𑗂�͂��Ă��ꂽ�B�X�e�C���ɂ́A�{���ɐ\����Ȃ��قǖʓ|�����Ă����������B�u���ꂪ�T���A���ŁA������O�Ȃ̂��B�v�Ƃ����̂������̕Ԏ��B�F�A�S��芴�ӂ��Ă���B
�@�Ō�̖K���ł��鋳��E�X�|�[�c�E�����Ȃɓ����B��b���ɒʂ���A�����Ƃ��َq�����������Ȃ��炨�b���f�����B
�@����E�X�|�[�c�E�����Ȃ���ɂ��āA�A�s�A�s�������w�B����c���������w��A���ؗ����X�Œ��H��ۂ�A�z�e���ɖ߂����B
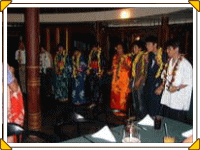 �@�@�@
�@�@�@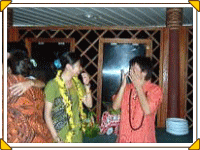 �@
�@
�E���ʂ�p�[�e�B�[
�@��V���߂��A���ʂ�p�[�e�B�[���n�܂����B���k�͗��߂�r���𒅂ēo��B�z�X�g�t�@�~���[���͂��ߋ���Ȃ�i�h�b�`�ȂǁA����K�₵����̕��X�����o�Ȃ����������B
�@���s�����O���Ȃ̕������A�����Ă���A�H�������Ȃ���̊��k�B���̌�A���{�̕����Љ���s�����B���{�̉̂��I���A�T���A�̐��k�B�ƂƂ��ɗx�����B���ɁA�T���A�̐��k�B�����߂�r���ɒ��ւ��ēo�ꂷ��ƁA���͍Ăщ₢�����͋C�ɂȂ����B
�@�����Ă��悢��Ō�̈��A�̎��B���k�B������ŁA��l��l�p��Ŋ��ӂ̋C�������ׂ̂��B�Ō�̈�l���b���I���ƁA�Z���搶�̃X�s�[�`�B�����ăT���A�̉̂��n�܂�A����ɍ��킹�Ă݂�Ȃŗx�����B�ƂĂ����������i�ł������B
�@�Ō�̃_���X���I���A�p�[�e�B�[���I��낤�Ƃ��Ă������̎��A�X�e�C��̐��k�̕��ꂪ�����o���A���{�̐��k�ƕ��������n�߂��B�����ė܂͂��̐��k�ցA����ɂ͎���̐l�X�ւƍL�����Ă������B���ɁA�z�X�g�t�@�~���[�Ɠ��{�̐��k�����͐S����ʂ��ɂ���ł����B
�W���P�X���i�y�j�Q�O���i���j�@�Ăуt�B�W�[��
 �@�@�@�@
�@�@�@�@
�E�ĂуA�s�A��`��
�@�T���A�𗣂�鎞�������B�P�X���ߑO�R���ɁA�ĂуA�s�A��`�ɓ����B���������ƂɁA��قǕʂꂽ�Z���搶�ƃX�e�C��̐��k������������ɗ��Ă���Ă����B�o�����r�[�ɕ��݂�i�߂�ԁA�p�������Ȃ��Ȃ�܂ł��݂��Ɏ��U�荇���B�{���ɖ��c�͐s���Ȃ��B�T���A�ł̎v���o�����ɔ�s�@�ɏ�荞�݁A�ߑO�T���R�T���A�Ăуt�B�W�[�ւƌ��������B
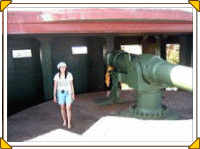 �@
�@ �@
�@ �@
�@
�E�t�B�W�[�ɂ�
�@�Q���ԂقǂŃi���f�B��`�ɓ����B���t�ύX�����z�����̂łQ�O���ߑO�U���R�T���ł������B�����Ƃ��Ɉē����Ă����������K�C�h���Ăяo�}���Ă����������B�����̃t���C�g�܂Ńt�B�W�[���w�ł���B
�@�܂��̓��~�C��ƃV�K�g�K���u�����w�B���~�C��́A��Q����풆�ɓ��{�R���}�������߂ɐݒu���ꂽ���̂������ʓI�ɂ͎g���邱�Ƃ͂Ȃ��A���͔������i�F�߂邱�Ƃ��ł���ό��n�ƂȂ��Ă���B
�@�ړ����̎ԑ�����͊C�݂ɐA����ꂽ�}���O���[�u���������B���{�̋��͑����A���������̂������ŁA�t�B�W�[�l�h���C�o�[�������̐A�тɎQ�������Ƃ̂��ƁB
�@���H�́A�C���h�l�̂���ɂ��ז����āA�C���h�̉ƒ뗿���𖡂�����B�䏊�ɓ���Ē����A�����̑̌��������Ă����������B�H��͂��̊Ԃ̊C�����B�씼���͓~�̎����̂��߁A�O�C�͗₽�����������������A�C�͉������A�M�ы����s��������̂�������قǂ��ꂢ�������B
�@�z�e���ɖ߂�A�[�H�̓z�e���̃��X�g�����ōς܂����B�����͂��悢��A���B�F�A�����C���������l�q�B�������ɔ�ꂪ�o�Ă���悤���B
�W���Q�P���i���j�@���{�ɋA��
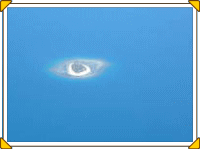 �@�@�@
�@�@�@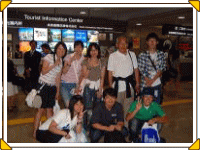
�E���c��`�ցA�����Ĉ��m��
�@�W���Q�P�����A�t�B�W�[�E�i���f�B���ۋ�`�ɓ����B�����ŁA���n�ł����b�ɂȂ����K�C�h����Ƃ��ʂ�B
�@��s�@�͌ߑO�P�O���T�O���A�荏�ʂ藣�������B�ቺ�ɂ̓t�B�W�[�̔��������X��������B�@���ł́A�H���̎��ȊO�͂قƂ�ǖ����Ă����l�q�B�X���Ԃقǂ̃t���C�g�̌�A�ߌ�T�����됬�c��`�ɓ��������B
�@���c��`�ł́A�O���Ȃ̕��Ƃ����ʂ�B�ꏏ�ɗ������钆�Ő܂ɐG��Ă��낢��Șb�����Ă��������A�\����Ȃ��قǐe�����Ȃ��Ă����B
�@���c�G�N�X�v���X�ɏ�Ԃ��A�����w�ɓ����B�����ŁA�h�e�`��Ƃ����ʂ�B�u�����A�����v�ƁA��������e���܂�Ă����B����̗��̗������Ǘ����Ă�������A�����Ȃ��Ƃ���ōׂ������z�������������B
�@�����w�ŗ[�H���w�����ĐV�����ցB�f�W�J���̎ʐ^�����Ȃ���v���o�b�����Ă���Ԃɕl�����B�ݗ����ɏ�芷���ĖL���w���o�R���A�ߌ�P�P���߂��ɖ{���w�ɖ��������B�ی�҂̕���c�����Z�̐搶�����o�}���Ă��ꂽ�B
�W���Q�T���i���j�@�݊y�����ɋA���̕�
�@�c�����Z�����ƌߌ�A�݊y�������K�₵�A�݊y�����ɋA���̂������ƌ��C�̕������B
�@��������͈�l��l�Ɍ��C�̗l�q�⊴�z��q�˂Ă�������A���k�����������Ƃ����\��ŁA���ꂼ��̑̌��⊴�z�����`�������B
�T���A�h����ʂ��Ă̏���
�@����̔h���́A�܂��ƂȂ��M�d�ȑ̌��ƂȂ����B
�@�T���A�ŁA���{�Ƃ͑S���قȂ鉿�l�ς╶���A�����K����̌����邱�Ƃ́A�������g�̑��݂��q�ϓI�Ɍ����������łȂ��A�������ۉ��Ȃ����{�l�ł�����{�l�ł��邱�Ƃ��ĔF�����邱�Ƃɂ��Ȃ�A���{������y��Ƃ������g�̃A�C�f���e�B�e�B���m�����邫�������ƂȂ�B�܂��A���i�ڂ��邱�Ƃ̂Ȃ����W�r�㍑�������͂��߁A�l�X�ȕ���œ����l�X�Ƃ̏o��́A�����̐i�H���l�����Ŏ����ɕx���̂ł������Ǝv���B���t�̖�����K���̈Ⴂ����A�����h���v���������ʂ��������悤�����A�����������Ƃ������̗ƂƂ��Ă�����̂����Z���̓����ł͂Ȃ����낤���B
�@�����b�ɂȂ����T���A�̍��Z���Ƃ���Ɍ𗬂�[�߁A�ł��邱�ƂȂ琶�U�ς�邱�ƂȂ��A������荇���A���݂��ɃT���A�Ɠ��{�����ԑ��݂ƂȂ��Ă�����Αf���炵���Ǝv���B�Ƃ�����A����̂��Ƃ��Ɏv���C�������A���̊C���z�����F���l���̕ɂ��Ă���邾�낤�B
�@�Ō�ɁAIFA�E�O���Ȃ̃X�^�b�t�̊F����A�����ăT���A�ł����b�ɂȂ����X�e�C��̂��Ƒ���A�A�x���E�J���b�W�̍Z���搶���͂��ߋ��E���Ɛ��k�̊F����A�܂��T���A�ŏo��������{�̉����@�ւ��Ƃ̊F����ɁA���܂��܂Ȍ`�ŏ����Ă��������Ȃ���A�W���Ԃ̌𗬎��Ƃ��I���邱�Ƃ��ł������ƂɁA�S��芴�Ӑ\���グ�A�T���A�h���v���O�����T�v�̕��I�������B
�u�c�����Z�́A�����P�W�N�x���{�EPIF�����n�����Z���𗬎��ƂɎQ�����܂����v�̃g�b�v��